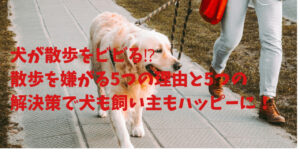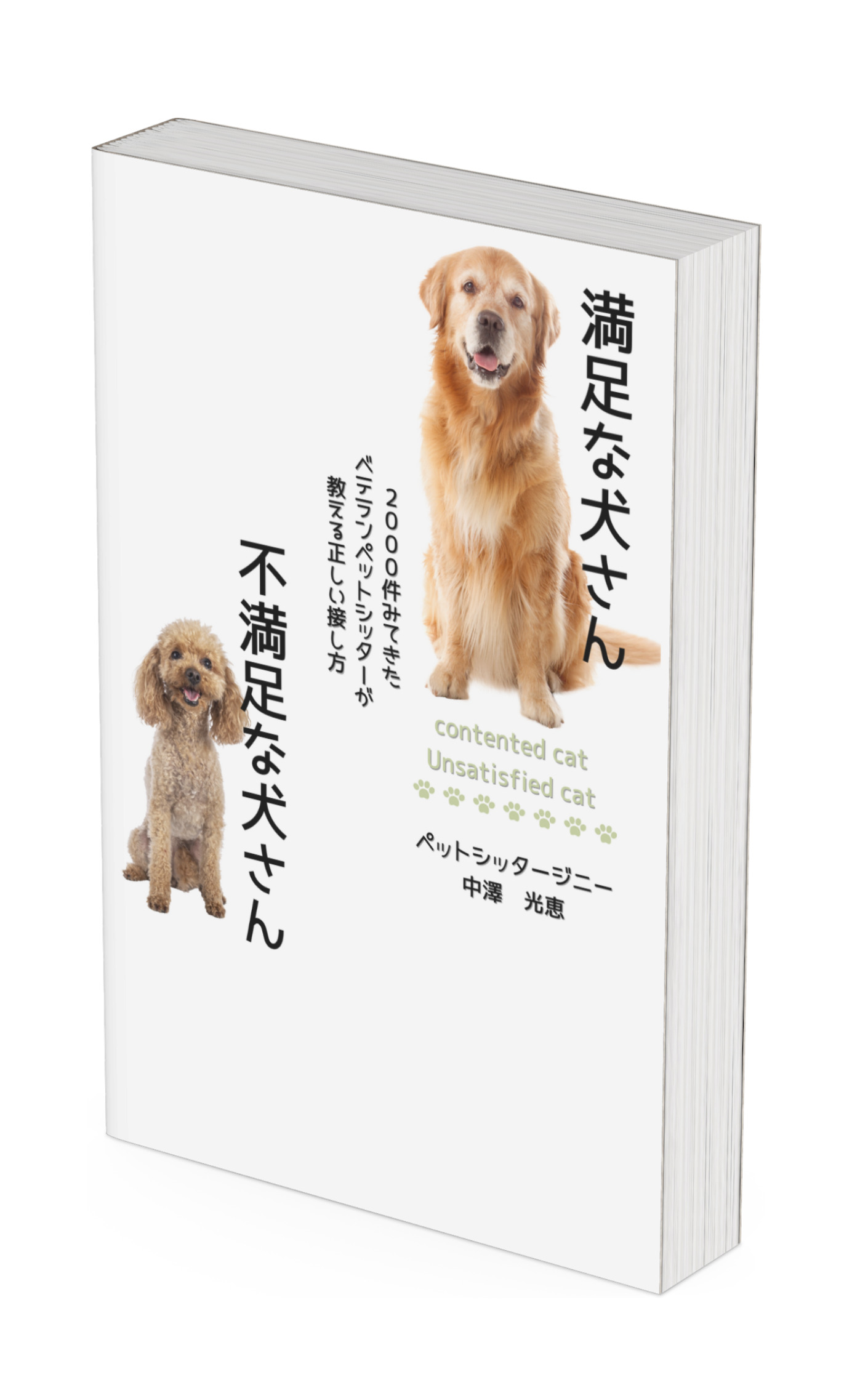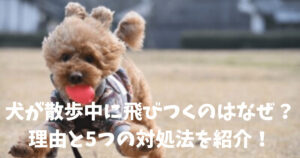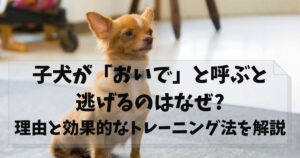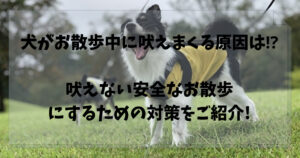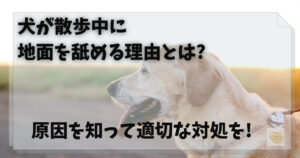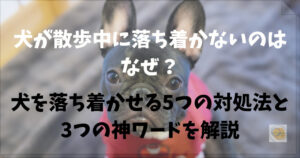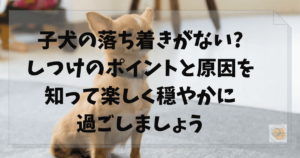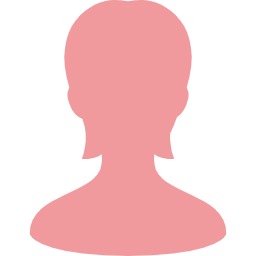 読者様
読者様うちの子は甘え鳴きがひどくて困っているの……
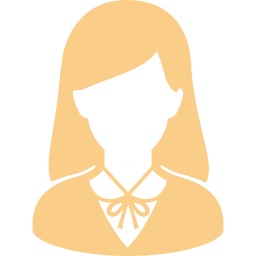
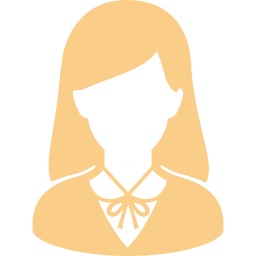
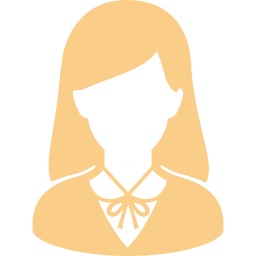
甘え鳴きには無視が効果的って聞いたけど本当?
ワンちゃんが甘えてくる姿は可愛い反面、対応に悩まされている飼い主さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
甘え鳴きといっても原因はいくつかあります。
原因によって対応が異なるため、しっかりと原因を理解することで問題解決の糸口が見つかってきますよ。
本記事では、甘え鳴きの原因と正しいしつけ方法についてご紹介します。
甘え鳴きについて理解し、ワンちゃんとの快適な暮らしを手に入れましょう。
今回の記事でわかること
- 甘え鳴きをする原因
- 甘え鳴きをするときのNG行動
- 甘え鳴きをするときの正しいしつけ方法
犬が甘え鳴きをする原因


犬の鳴き声は、飼い主さんへ気持ちを伝えるためのコミュニケーションツールの1つです。
鳴く頻度が高いと、ときには「うるさいなぁ」と感じてしまうこともあるでしょう。
しかし見逃してはいけない大事なサインを送っていることもありますので、注意が必要です。
甘え鳴きの原因を理解して、ワンちゃんとの信頼関係向上の参考にしてくださいね。
甘えたい
「もっと遊んでほしい」「もっと自分に注目してほしい」という気持ちを、甘え鳴きで表現しています。
ウルウルした目で訴えられると、思わず構ってあげたくなりますよね。
しかしワンちゃんの訴えに常に対応していると、「鳴いたら構ってもらえるんだ!」と学習してしまうこともあるので、対応の加減が難しいところです。
どれだけ可愛くても、四六時中ワンちゃんの相手をするのは困難です。
対応できるときは存分に甘えさせてあげて、難しいときは大人しく待つことをワンちゃんに教え、メリハリのある生活を送ることで甘え鳴きも軽減できますよ。
寂しさや不安を感じている
飼い主さんが視界から消えたり、出掛ける準備を始める姿を見たりすることで、寂しさを感じ甘え鳴きをします。
また、苦手なものや初めての出来事に出会ったときに、不安を感じて甘え鳴きをすることもありますね。
犬は群れで生きる動物なので、孤独を感じる環境は大きなストレスになってしまいます。
しかし何に対してストレスを感じているのかは、犬それぞれ違うので見極めが肝心です。
「お留守番の時間が長い」「飼い主さんとのコミュニケーション不足」など、ストレスとなっていることはないか行動を振り返って確認してみましょう。
犬の感じている寂しさや不安に気づかず放置してしまうと、不安分離症になるワンちゃんもいます。
ワンちゃんが安心して暮らせる環境を整えてあげると、甘え鳴きが減る傾向がありますよ。
痛みなどの身体的な不調を訴えている
痛みや何らかの体調不良を訴えている可能性も考慮する必要があります。
鳴き声だけではなく、いつもとは違った仕草を見せることが多いので、ワンちゃんをよく観察してくださいね。
以下のようなことがないか、チェックしてみてくださいね。
- 目がうつろでぼんやりしている
- 動いたり食べたりする元気がない
- 震えている
- 寝ている時間が多くなる
- 呼んでも反応が鈍い
- 触られるのを嫌がる
少しでもワンちゃんの様子がおかしいと感じた際には、必ずかかりつけの動物病院に相談しましょう。



ワンちゃんからの小さなSOSをいち早く察知してあげられるのは、飼い主さんだけです!
犬が甘え鳴きをするときのNG行動


ワンちゃんの甘え鳴きが続くとき、飼い主さんはどんな対応をされていますか?
対応を間違えると、ワンちゃんとの関係に悪影響を及ぼす可能性があります。
甘え鳴きに対するNG行動をご紹介しますので、意図せず行っていないか確認してみてくださいね。
要求に寄り添いすぎる
「遊んでほしい」「おやつがほしい」などの要求に寄り添いすぎると、甘え鳴きが酷くなりやすいです。
犬は賢いので、「鳴けば要求が通る」と学習してしまいます。
常にワンちゃんの様子を気にかけておくことはとても大切ですが、ワンちゃんの要求に振り回されないように気をつけましょう。
鳴いている間は注意を向けずにそっとしておき、鳴き止んだタイミングで要求に応じることがポイントです。
ワンちゃんに「甘え鳴きをしなくても気持ちを受け止めてもらえるんだ」と、感じてもらえるように接してくださいね。
静かにさせるためにおやつを与える
静かにしてほしくておやつを与える行為は、甘え鳴きを悪化させてしまいます。
おやつを食べている時間は静かにしてくれるので、飼い主さんは楽ですよね。
しかしほっとしたのも束の間、食べ終えたら「もっとほしい!」と再び鳴き始めることも少なくありません。
犬は一度学習したことは、意地でも貫き通す傾向があります。
おやつがもらえるまでワンちゃんが鳴き続け、根負けしておやつを結局あげてしまう飼い主さんが多いです。
手っ取り早く結果を出そうとせずに、地道にしつけをし続ける方が結果的には早く成果を出せますよ。
叱る
犬を叱る行為は避けましょう。
人間に対して恐怖心を抱かせるだけで、「してはいけないことをした」と犬が思えないからです。
ワンちゃんによっては怯えや恐れから、人間とのコミュニケーションを諦めてしまうかもしれません。
大きな声を出したり感情をぶつけたりするような𠮟り方は、以下のような悪影響を及ぼします。
- トラウマになってしまう
- 自己防衛のために攻撃的な態度になる
- 飼い主さんとワンちゃんの信頼関係が崩れる
- 叱られた理由がわからず同じことを繰り返す
中には反応してくれること自体に喜び、「飼い主さんに構ってもらった!」と勘違いして、甘え鳴きを悪化させてしまうケースもありますよ。
観察せずに無視を貫く
「要求に応えすぎてはいけない」という考えが先行し過ぎて、ワンちゃんの様子をよく観察せずに無視を貫くことは得策とは言えません。
何かを伝えようとしている鳴き声には、命に係わる危険など見落としてはいけないサインが隠れている可能性があるからです。
人間の赤ちゃんと同じように、犬は声や仕草で飼い主さんとコミュニケーションを図ります。
一生懸命訴えても反応してもらえなかった経験は、甘え鳴きをエスカレートさせる要因にもなり得ます。
鳴いている理由を決めつけず、まずはワンちゃんの様子をしっかり観察してみてくださいね。
犬が甘え鳴きするときの正しいしつけ方法


人間がそれぞれ性格や生まれ持った気質が違うように、犬にもそれぞれ違った個性が存在します。
甘え鳴きに対する正しいしつけを行っていくためには、犬の持つ個性の理解が不可欠です。
まずはしっかりワンちゃんを観察して、ワンちゃんに合ったしつけ方法を見つけましょう。
適度な関わりで寂しさを解消してあげる
存分に甘やかすときと自立心を高めるときのメリハリのある対応で、ワンちゃんとの距離感を保ちましょう。
可愛くてつい求められると応えてあげたくなりますが、応えてばかりいると飼い主さんへの依存を助長してしまいます。
改善策としては、あなたの生活のルーティンにワンちゃんと過ごす時間を組み込んでみてください。
その時間はしっかりワンちゃんと向き合い、存分に甘えさせてあげましょう。
充実した時間への満足感と共に、「一日のどこかでちゃんと構ってもらえる時間がある」という安心感にも繋がります。
それでも足りなさそうであれば、優しく「もうおしまいだよ」と伝えましょう。
おしまいと伝えた後は、名残惜しくても中途半端に構ってはいけません。
ワンちゃんの要求に振り回されず、飼い主さん主導の接し方を心掛けてくださいね。



おしまいのサインをご家族で共有しておくと、より伝わりやすいですよ。
見逃してはいけない要求にはすぐに応える
以下のような要求のときは、すぐに応えてあげましょう
- 喉が渇いている
- トイレに行きたい
- どこかに痛みがある
生理的欲求が満たされない環境は、大きなストレスを感じやすいです。
ワンちゃんの命にも関わることもあるので、見落とさないようにしてくださいね。
安心して過ごせる環境を整えてあげることで、甘え鳴きの回数を減らすことにも繋がりますよ。
安心感を与える
ワンちゃんが不安や恐怖を訴えている場合は、その原因を取り除き気持ちを逸らしてあげましょう。
不安や恐怖から助けてくれる飼い主さんの行動は、ワンちゃんに安心感を抱かせます。
行動例として、以下の言動があげられます。
- 抱っこする
- 安心できるスペースを確保する
- 飼い主さんのにおいが付いた衣類や毛布を渡す
- 落ち着いたトーンで「大丈夫」など優しく伝える
「自分は大切にされている」という自信にもなり、信頼関係も深まめられますよ。
遊びながら離れる練習をする
心理的にも物理的にもワンちゃんとの距離が近すぎると必要以上に依存的になり、甘え鳴きをしやすくなります。
ワンちゃんがひとりになる時間を初めは数秒~数分と徐々に時間を増やし、離れる練習をしましょう。
「離れても大丈夫」「待っていれば飼い主さんは必ず自分の元に戻ってきてくれる」という感覚をワンちゃんに覚えてもらう必要があります。
犬は過去の経験から学習する能力を持っています。
根気強くコツコツと離れる練習をすることで、ワンちゃんの自信となり自立心を育むことに繋がりますよ。
離れる練習を成功させるためには、飼い主さんがいない時間も楽しく過ごしてもらえるような工夫が大切です。
練習する際には、以下のポイントを意識してみてください。
- 知育玩具等でひとり時間を退屈させないようにする
- 普段から長時間一緒にいないことを意識する
- 外出の雰囲気を感じさせないようにサッと離れる
- お留守番前にはお散歩等の適度な運動をしてエネルギーを発散させる
ポイントは離れる練習を一気に進めないことです。
ワンちゃんは飼い主さんの行動や気持ちを敏感に察知しています。
少しでもワンちゃんが不安そうな表情や仕草が見受けられたら、無理せず練習のペースを落としましょう。
焦らずワンちゃんのペースに合わせて練習することが、結果的に甘え鳴き改善の近道になります。
一貫した姿勢を示す
ワンちゃんに対して一、貫性のある態度や行動を示すようにしましょう。
飼い主さんの気分や都合で態度を変えられると、ワンちゃんが混乱してしまいます。
犬は人間の感情や行動を敏感に感じ取るので、飼い主さんの一貫性のない姿勢は精神を不安定にしてしまいます。
飼い主さんが明確な行動基準を示すことで、ワンちゃんのストレス軽減に繋がります。
一貫することとして、以下の行動を意識してみてください。
- おやつの与え方やしつけ方法を家族内で統一する
- 同じコマンドを使う
- 何かに失敗してもフォローしてあげる
- 犬の良い行動は積極的に褒める



飼い主さんのことを「自分の良き理解者である」とワンちゃんが感じてくれるような姿勢を示しましょう。
甘え鳴きの原因を見極めて愛犬との絆を深めよう!
今回は犬の甘え鳴きの原因としつけ方法についてご紹介しました。
甘え鳴きの原因は、以下の通りです。
- 甘えたい
- 寂しさや不安を感じている
- 痛み等の身体的な不調を訴えている
身体的な不調を訴えているときは、特にワンちゃんをよく観察し対応してくださいね。
甘え鳴きに対するNG行動は、行わないように注意しましょう。
- 要求に寄り添いすぎる
- 静かにさせるためにおやつを与える
- 叱る
- 観察せず無視を貫く
習慣になっていると、なかなか難しいかもしれません。
しかしワンちゃんとの関係に悪影響を及ぼすことになりかねませんので、意識して行動を変えていきましょう。
正しいしつけ方法を用いると、ワンちゃんの甘え鳴きを改善していくことが可能です。
- 適度な関わりで寂しさを解消してあげる
- 見逃してはいけない要求にはすぐに応える
- 安心感を与える
- 遊びながら離れる練習をする
- 一貫した姿勢を示す
ご家族がいる場合はワンちゃんが混乱しないように、しつけ方法を共有して行ってくださいね。
犬が甘え鳴きをする理由はさまざまです。
飼い主さんがワンちゃんと真摯に向き合う姿勢は、家族としての絆を深められるでしょう。
ワンちゃんの伝えたい気持ちを決めつけたり侮ったりせずに、きちんと甘え鳴きの原因を見極めて、ぜひワンちゃんに合ったしつけ方法を見つけてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。